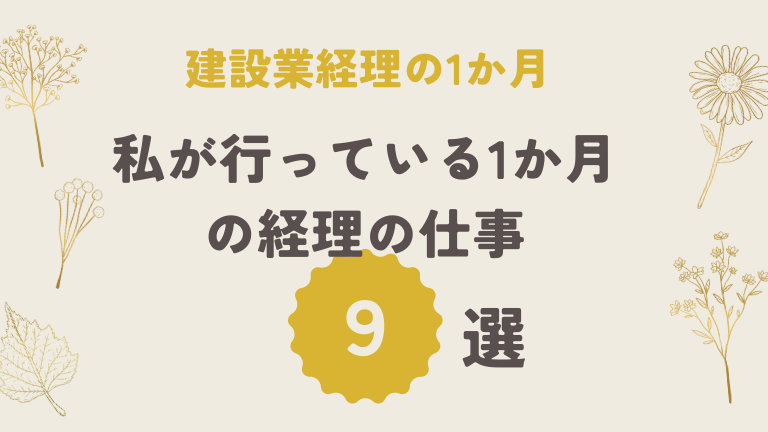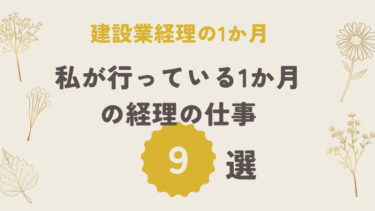こんにちは、ルビリナです
私は建設業の会社で経理を行っています
経理という仕事がお金に関する仕事というのは、何となくイメージができる人も多いと思いますが、具体的に何してるの?という声を耳にします
このため、建設業で行う経理の仕事がどのようなものか、私の具体例をもとにご説明します
今建設業で働いている経理の方や、製造業で働く経理の方などに少しでも参考になればと思います
建設業の経理業務について
- 業務日報の確認・原価情報入力
- 経費精算処理(小口現金)
- 銀行対応(入出金・税金支払い)
- 支払請求書の確認・各部への確認用アップロード対応
- 資金繰り管理
- 会計ソフトへの入力
- 完成工事の分析、部門ごとの報告資料作成
- 請求書作成
- 各種保険内容の対応(事故対応・更新等)
毎日ルーティーンとして行うことや、1か月のうち、どこかで必ず行う内容
また、1年間のうちにたまに発生する仕事を列挙致しました
これらの業務は私の他2名で行っているので、それほど忙しい日々が続くというわけではありません
ただし、税理士による毎月のチェック(これを税理士の巡回と言われます)を行うまでは追われる日々が続きます
1.業務日報の確認・原価情報入力
現場の方は毎日仕事が終わってから業務日報を作成します
内容としては、
- 日付・現場名
- 誰と行き、どんな車両を使用したか
- 外注業者はいたか?いた場合は車両を使ったか(貸したか)
- 給油や高速道路の使用があったか
等を業務日報にまとめます
この内容が、その工事に関する「原価」の情報に繋がってきます
このため、「内容に矛盾がないか」や「記入間違いがないか」のチェックを行います
有料道路などは休日割引などもあるため、曜日を注意する必要があります
私の会社の場合、自社で警備会社をやっているので、自社警備を使用したのか、外部の警備会社を使ったのかによっても金額が変わります
外注の人でも、人によって単価が異なることがあるので、単価が異なる方が外注として入った場合などは原価を登録する際に注意が必要です
ここまで業務日報のチェックが終わった後は、原価情報を別のソフトで入力をします
私の会社の場合「どっと原価NEO」という原価管理ソフトを使用しています
建設業界で働く人にとってはメジャーな原価管理ソフトのようです
比較的使いやすく初心者が導入しやすく、他の会社の営業担当と話をした際にも必ずこのソフトの名前は知っていました
原価管理ソフトでは
- 工事登録(初めての現場では)
- 労務費の登録
- 使用車両の登録
- リース品の登録
- 有料道路の登録
- ガソリン代の登録
- 外注業者の登録
を行います
使う資料は先ほどの業務日報を使うため、日報に記載されていた内容がベースになります
初めて現場に入ったような工事の場合、工事についての番号(工事番号)や工事名などの情報がないため、登録を行います
こうすることで、工事の登録ができ、原価の集計をしていくことが可能になります
自社の社員の単価や自社の車両の単価については事前に決まっています
人で決めることもできますが、原価情報を入力する際に1人1人選択していては時間が掛かりすぎるため、

- 一般社員
- 主任
- 係長以上
- 報告書係
といった4種類の単価設定を行い、業務日報に記載される人がどれに当たるかを判断して入力します
勘がいい人は気づいたかもしれませんが、「報告書係」という人は現場に入りません
報告書係という人たちは、現場が行った内容を役所等に提出する用に資料としてまとめる仕事をしている人たちです
報告書が必要な現場については、この報告書の完成をもって工事の完了となります
このため、報告書係の人件費も工事の原価(労務費)に含める必要があります
リース品などはリース会社から届いた請求書をもとに入力します
一旦この場では何も登録を行いません
最後に外注業者については、ある程度事前に単価が決まっているため、基本的に入った時間に対して原価の登録を行います
外注業者から、
○○時から○○時まで△△という現場で▢人作業をしました
という報告書を毎回出してもらいます
この内容で登録を行い、届く請求書と突合をして一致していることを確認し、お金を支払います

2.経費精算処理(小口現金)
現場で必要となる工具等がある場合、現場の方が自分のお金で買う場合があります
本来であれば、会社でまとめて購入すればよいのですが、時間的な問題や距離的な問題で難しいときがあります
そんな時、一旦個人で立替をしてもらい、後日精算するという流れになります
この生産の処理を経費精算処理と呼びます
このうち、少額の精算であることから、経理にて管理をしている金庫(小口現金)からお金を支払います
なるべくは現金精算を減らしていきたいのですが、出張先で必要なものを申請して出張先まで届けるということは現実的ではありません
また、給与振り込みに混ぜることも可能なのですが、一部の人は(昔からの習慣?)この立て替えたお金をへそくりにしている人がいるようです
転職した人から聞いた話ですが、他の業界でも現場系の方の世界ではあるあるな内容だそうです
このため、建設業界としては小口現金がなくなる未来はもう少し先のような気がしますね
この処理の注意点として、申請された内容のチェックはもちろんですが、同時に経理資料として「小口現金出納帳」を作成します
こちらへの転機処理を間違えてしまうと会計ソフトへの入力の際にも間違った情報が転記されるので正確に行う必要があります
また、申請されている商品が「現場で使うもの」か「事務所でみんなが使うもの」かを確認します
これは会計ソフト上での消費税区分の違いに影響しますので必ずチェックをします

3.銀行対応(入出金・税金支払い)
銀行がお客さんの所でお金を集金するという仕事は10年くらい前から少なくしていく傾向にあります
しかし、小切手などはATMで入金できないため、銀行の方に対応をして頂く必要があります
また、税金の支払いや約束手形の取立の手続きなど、銀行でなければ処理ができない業務もあります
こんなとき、お付き合いのある銀行の営業担当にお願いをして取りに来ていただきます
こちらとしては、書類に押印をするくらいなので、大した事務処理はありません
銀行員の立場としては行くきっかけが少ない取引先に対して訪問のチャンスとなります
経理担当者は社長と話をする機会も多いため、会社の状態や社長の思いなどを聞いてくることがよくあります
分かる範囲内で協力し、長い話にならないように注意をします
4.支払請求書の確認・各部への確認用アップロード対応
建設業界というのは、まだまだアナログなところが多い業界です
理由としては、ひとり親方や零細企業など少人数で事業を行っている方が多いためです
IT業界では請求書の授受については電子化されるなど、デジタル化が進んでいます
私の前職であるアパレル業界もWEB-EDIやBMSといった通信で請求データを送る会社が多くなり、紙での請求書というのは少なくなっていました
残念ながら建設業界はまだ、こういった流れに乗ることができていないのが現状です
このため、1枚1枚紙の請求書の中身を目で見て精査する必要があります
確認する内容としては、
- 個別金額・合計金額の確認
- 税率、消費税額の確認
- 請求書の支払日の確認
- インボイスの確認(23年10月より)
といった内容です
そもそも、発注内容があっているかの確認も必要なため、発注担当者へ発注内容の確認を依頼します
CMでもよく目にする「インボイス」についても、23年10月より開始されることから、チェックをしていく必要があります
こちらが作成する請求書に関しては、営業担当より経理へ
- 請求先
- 請求内容
- 請求金額
の指示を頂きます
ここで大切なのが、経理側としても請求先を把握しておくことです
もし、営業担当が請求することを忘れてしまっては会社の損失となってしまいます
このため、経理としても「今月〇〇で請求があるはず」と予測を立てています
予測に反して請求の依頼がない先については、こちらから確認を行い、要不要の確認をします
そして、入金がされるまでは「売掛金」という名前(勘定科目)で管理します
入金がされたときにこの金額が0円になれば問題ありませんし、差異が出る場合はその原因の追究を行います
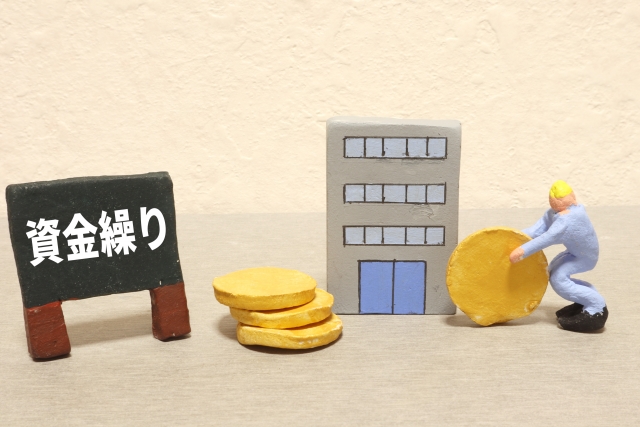
5.資金繰り管理
経理の大切な仕事の1つに「資金繰りの管理」があります
相手に対する支払いや税金、社会保険料等様々な費用が会社の口座から支払いが発生します
この時に預金残高が無ければ支払いができないため、
- 他の銀行口座から預金を移す
- 借入をして預金を増やす
- 手形を割引or取立に出す
等の預金を増やす取組をする必要があります
こういった事態を事前に把握することが資金繰り管理となります
実際には預金残高から、今後引落される見込みの費用を洗い出し、資金が枯渇するタイミングがないかシュミレーションをします
この時注意すべき点として、毎月発生する社会保険料の支払いなどは忘れることはないと思いますが、労働保険料や消費税の支払いなど、スポット的に発生する支払いを忘れないようにしましょう
年間でいつ、どのような費用の引き落としが発生するかを事前にまとめておくことがミスを防ぐポイントになります
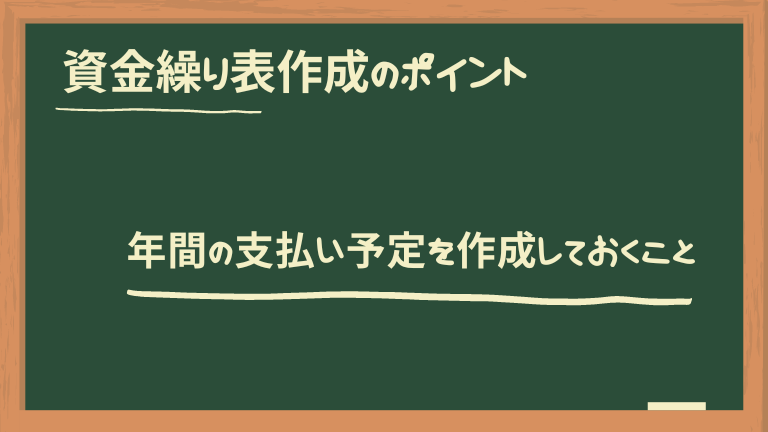
6.会計ソフトへの入力
私の会社の場合TKCのFX4クラウドという会計ソフトを使用しています
TKCという会社自体は耳にしたことのある人が多いのではないでしょうか?
前月1か月の間で発生した取引をFX4クラウド上に入力していきます
入力内容は、
- 預金出納帳
- 現金出納帳
- 掛け取引・未払い費用
- 減価償却
- 仕掛計上
などです
預金、現金出納帳については、日々の動きの記帳内容を入力するのですが、現場で使用した費用か、そうでないのかの確認や、材料なのか消耗品なのか取引の内容を理解しておかなければ入力ができません
このため、請求書等が届いたタイミングで請求内容の理解をするようにします
また、売掛金については、売上入金のチェックも同時に行います
多くの場合は会計ソフトの機能の中に売掛金管理があり、現在残っている得意先の売掛金残高が分かるようになっていると思います
入金が遅れている先については、こちらから先方の経理の方に連絡して状況の確認を行います
また、買掛金や未払い費用については、私の処理に漏れがないかのチェックも含めて残高が残っていないかチェックをします
減価償却については、金額の決定は税理士にお願いしています
日商簿記の知識でやるのであれば、出来そうな気もしますが、耐用年数を何年に設定するのかというのが、私自身よくわかっておりません
仕訳については、毎月同額で同じ仕訳を切ればよいだけです
最後に仕掛ですが、先に述べた通り、現場の方が作成する業務日報や請求書で発生原価を確認します
この中で今月請求が起こっていない工事が仕掛となります
仕掛となったものの製造原価の総額を計算し、
- 前月仕掛計上の逆仕訳(相殺仕訳)
- 当月仕掛の計上
の2つの仕訳を切ります
この結果、当月発生した仕掛分のみ、製造原価から除くことができます

7.完成工事の分析、部門ごとの報告資料作成
終わった工事について、結果をまとめます
具体的にはどれだけの粗利が残ったかやその内訳をまとめます
私の会社の場合、部門がいくつか分かれているため、それぞれの部門ごとで集計をします
工事が多いと大変ですが、数値の速報値を知っているのは経理ですので、伝えることによって経営者や部門長、営業担当の今後の活動内容が変わってきます
この辺りは管理会計となりますので、基本的には会計ソフトや原価管理ソフトから出力されるデータをもとにエクセルで集計、まとめを行っています
出来るだけ見やすさを重視して無駄な情報はそぎ落とした方が相手の理解が早くなります
会計の知識が全くない人にとっては数字の羅列でしかないので、出来るだけ重要な数値のみに絞り、必要に応じて細かい情報を提供するというスタイルの方がよいのかなと考えています
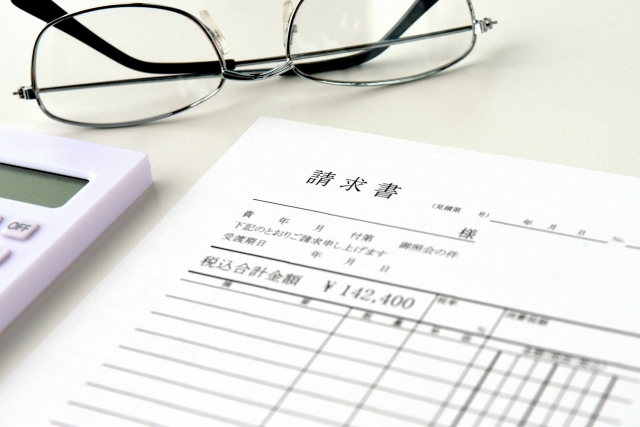
8.請求書作成
月次の会計処理と並行して請求書の作成を行います
基本的には営業担当の方より指示を頂き、作成します
私の会社の場合は原価管理ソフトの機能で請求書を作成できます
ここで作成した請求書の情報が、原価管理ソフト上で売上集計されますので、月の売上内容の把握をするときに役立ちます
どの現場で、いくらの金額で請求書を出したのか(売上たのか)が一覧で出てきますので、その内容をもとに会計ソフトに入力するという流れです
私の会社では対応しておりませんが、売り上げのデータをエクスポートして、会計ソフトにインポートすることもできるようです
これを行えば、1つ1つ仕訳を切らなくても会計ソフトにデータを入力することができるようです
会計ソフトによってはこの辺りも自動連携してくれるソフトがありそうな気はしますね
請求書の作成が遅くなってしまうと、相手の締め日に間に合わなくなり、入金が遅くなってしまいます
この結果自社の資金繰りが厳しくなることが予想されるため、請求ができる先に対しては出来るだけ早く請求書を発送することが大切です
余談ですが、FREEEのソフトで、請求書をアップロードして頂く場所を作り、そこのURLをお客様共有することでWEB上で請求書の確認をすることができるようになるサービスがあるようです
月額5,000円でできるようで、現在検討中です

9.各種保険内容の対応(事故対応・更新等)
この内容自体は総務の仕事に近い気がしますが、後々経理でも内容を把握しておく必要があるため、対応するようにしています
保険金が入ってきた場合や、保険会社から支払いをした場合などは消費税の分け方が変わります
ちょっと難しい話になるので、ここでは割愛しますが、経理としては保険金で支払ったのかどうかは最低限把握しておきたいところです
ここが把握できていれば、顧問の税理士等に相談すればどのように処理をすればよいか指示を頂けます
長くなりましたが、これらの仕事が大まかな私が行っている建設業の経理の1か月の仕事内容です
私の会社の場合、部門ごとの売上や粗利を会計ソフト上で把握をさせる(部門別会計)を行っているので、これまでも内容に部門の情報も加味させます
Aという材料仕入れはどの部門で使用する材料か?
Bという売上は〇部と△部が2:1の割合で仕事をしたため、売上もそれに応じて案分する
といった内容を行います
ここについては、十分にできていないのが実情ですね
部門別会計を行うと恐ろしく仕分けの数や部門がどのように関連しているのかを把握していなければいけないため、漏れが出てしまいます
この点についてはつい先日も社長よりお言葉を頂いたところです
経理をまとめる立場にある以上は、この点について来期より改善しなければなりません
部門別会計でも困った点や試した方法などがあれば、ここでお伝えしていきたいと思います
【良ければ、下記をクリック頂けると励みになります】
にほんブログ村